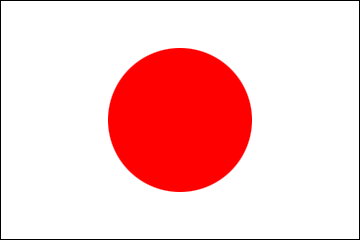大使室より(マトルカ社訪問)
令和3年9月6日



「アークティック・チャー」という魚をご存じでしょうか?
日本では「北極イワナ」とも呼ばれるこの魚。
「イワナ」というと、私には渓流に暮らす小さい魚のイメージがあるのですが、こちらの「北極イワナ」の方は、シャケ(サーモン)やマス(トラウト)の一種で、成魚ともなるとかなり大型の魚です。肉もシャケに似たピンク色の肉で、刺身としても、また調理して食べても、とてもおいしい魚です。
先日、レイキャビクから車で40分ほどのグリンダビークに、こうした魚を養殖して加工、出荷しているマトルカ社を訪問しました。ここは古くから漁港として栄えたところです。
アイスランドには地の利を活かしたさまざまなユニークな発想のイノベーション企業がありますが、この会社もその一つです。
CEOのアルニさんに事業の概要をご紹介いただきました。
実は、アルニさんは文部科学省の奨学金で、埼玉大学にも留学した経験があり、日本語もお上手。というわけで今回、説明は日本語でしていただきました。(このお名前、アイスランド語の発音は実際には「アウルトニ」に近いと思うのですが、ご本人、外国人相手には、発音しやすく「アルニ」と自己紹介されているとのことでしたので、ここでもそうお呼びしたいと思います。)
「アークティック・チャー」は、天然では、湖や川など、塩分の少ない水の中で暮らす淡水魚ですが、鮭と同じく、成長の過程の一部を海で過ごす仲間も居ます。
同社の魚の養殖の特徴は、陸上に設置したプールのような施設で養殖を行うこと。水は、この地の溶岩石で濾過された豊富な地下水を使います。この水は海水からしみ出す塩分をわずかに含み、飲用には適しませんが、この魚の成長には適しています。卵からふ化した稚魚は、塩分の低いアイスランド南部の別の場所の施設で150グラムほどの大きさになるまで育てられ、その後、ここに移されます。
海上に生け簀を設けての鮭の養殖は、ノルウェーやチリ、アイスランドでも行われていますが、寄生虫の管理が難しく、かつては抗生物質の投与が付近の海水汚染の原因となったこともあります。いまではそのような投与は規制されているそうですが、この会社での養殖では、きれいに濾過された地下水を利用するため、そもそも、そのような心配がありません。
アークティック・チャーの切り身を少しお譲りいただき、刺身にしていただいたのですが、柔らかい質感で大変おいしい味でした。
残念ながら、マトルカ社のつくる魚は日本市場にはまだ輸出されていません。
日本市場ではこの魚はあまり知られておらず、市場価値が確立していないことに加えて、新鮮さが売りの魚ですから、輸送手段の有無がネックになります。北米へは空輸、欧州へはアムステルダム港への定期便の船で輸送されるのだそうです。日本に輸出するとすれば、高級な生鮮品として買い手がつくことが前提になりそうですね。
豊富な漁場を近海に抱え、海からとれる魚を相手とする漁業を基幹産業として今まで発展してきたアイスランドですが、魚の資源量は変動も大きく、昔はたくさんとれていた魚が今はとれなくなった、といった話は少なくありません。天然の水産資源に頼るのには限りがあります。
マトルカ社の養殖はそうした資源制約がなく、まだまだ拡大の余地がありそうです。
日本では「北極イワナ」とも呼ばれるこの魚。
「イワナ」というと、私には渓流に暮らす小さい魚のイメージがあるのですが、こちらの「北極イワナ」の方は、シャケ(サーモン)やマス(トラウト)の一種で、成魚ともなるとかなり大型の魚です。肉もシャケに似たピンク色の肉で、刺身としても、また調理して食べても、とてもおいしい魚です。
先日、レイキャビクから車で40分ほどのグリンダビークに、こうした魚を養殖して加工、出荷しているマトルカ社を訪問しました。ここは古くから漁港として栄えたところです。
アイスランドには地の利を活かしたさまざまなユニークな発想のイノベーション企業がありますが、この会社もその一つです。
CEOのアルニさんに事業の概要をご紹介いただきました。
実は、アルニさんは文部科学省の奨学金で、埼玉大学にも留学した経験があり、日本語もお上手。というわけで今回、説明は日本語でしていただきました。(このお名前、アイスランド語の発音は実際には「アウルトニ」に近いと思うのですが、ご本人、外国人相手には、発音しやすく「アルニ」と自己紹介されているとのことでしたので、ここでもそうお呼びしたいと思います。)
「アークティック・チャー」は、天然では、湖や川など、塩分の少ない水の中で暮らす淡水魚ですが、鮭と同じく、成長の過程の一部を海で過ごす仲間も居ます。
同社の魚の養殖の特徴は、陸上に設置したプールのような施設で養殖を行うこと。水は、この地の溶岩石で濾過された豊富な地下水を使います。この水は海水からしみ出す塩分をわずかに含み、飲用には適しませんが、この魚の成長には適しています。卵からふ化した稚魚は、塩分の低いアイスランド南部の別の場所の施設で150グラムほどの大きさになるまで育てられ、その後、ここに移されます。
海上に生け簀を設けての鮭の養殖は、ノルウェーやチリ、アイスランドでも行われていますが、寄生虫の管理が難しく、かつては抗生物質の投与が付近の海水汚染の原因となったこともあります。いまではそのような投与は規制されているそうですが、この会社での養殖では、きれいに濾過された地下水を利用するため、そもそも、そのような心配がありません。
アークティック・チャーの切り身を少しお譲りいただき、刺身にしていただいたのですが、柔らかい質感で大変おいしい味でした。
残念ながら、マトルカ社のつくる魚は日本市場にはまだ輸出されていません。
日本市場ではこの魚はあまり知られておらず、市場価値が確立していないことに加えて、新鮮さが売りの魚ですから、輸送手段の有無がネックになります。北米へは空輸、欧州へはアムステルダム港への定期便の船で輸送されるのだそうです。日本に輸出するとすれば、高級な生鮮品として買い手がつくことが前提になりそうですね。
豊富な漁場を近海に抱え、海からとれる魚を相手とする漁業を基幹産業として今まで発展してきたアイスランドですが、魚の資源量は変動も大きく、昔はたくさんとれていた魚が今はとれなくなった、といった話は少なくありません。天然の水産資源に頼るのには限りがあります。
マトルカ社の養殖はそうした資源制約がなく、まだまだ拡大の余地がありそうです。