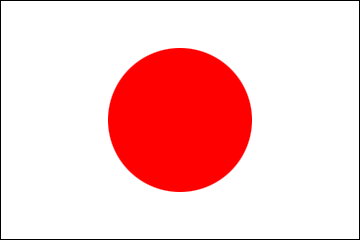大使室より(地熱発電のさまざまな形)
令和5年6月15日



地熱発電所の話ばかりが続いて恐縮ですが、これがその第3弾になります。
地熱発電にもいろいろな方式があり、地中から吹き出る水蒸気を直接発電に使う方式は「フラッシュ」方式と言われます。ヘトリスヘイジも、スヴァルツエンギも、いずれもこの方式です。こういう発電方法には高熱の熱水源が必要。そういう熱源を探すことは容易ではありません。実際に掘削してみたら予想より温度が低く、発電向けには使えない、という可能性も考えられ、事業にはリスクも伴います。
私が次に訪れたのは、フルージルという南部の地にあるより小さい発電施設。いわゆるゴールデン・サークルの近辺。ちなみに近くには、「シークレット・ラグーン」と名付けられた施設もあり、ここはちょっとした観光施設にもなっています。(温泉横に作られた古いスイミング・プールをきれいに改装しただけに過ぎないのですが。ちょっと面白いところではありますが、どこが「秘密」なのかはいまだ謎です。)
地域の発電事業者によりこの施設が建設されたのは2018年のこと。新しい施設ですが、発電能力はわずかに600kWに過ぎません。しかし、ここには、「バイナリー」方式といわれる最新の発電方式の施設が設置されています。利用されているのは、117度の比較的低温の温水で、8機のクライムオン社(スウェーデン)のジェネレーターにつながり、低温で揮発する触媒を通じてタービンを回し、地域に必要な電力を生み出します。
この発電施設の運営者は、今では、スウェーデン資本のベースロード・キャピタル社の子会社となっています。ベースロード・キャピタル社の子会社は、実は日本や台湾にもあり、小規模ながら、低温熱源を地熱発電に活用する試みがなされています。こうした低温熱源の利活用は、電力料金の低いアイスランドよりも、むしろ、日本のようなところに向いているのかもしれません。
地熱発電にもいろいろな方式があり、地中から吹き出る水蒸気を直接発電に使う方式は「フラッシュ」方式と言われます。ヘトリスヘイジも、スヴァルツエンギも、いずれもこの方式です。こういう発電方法には高熱の熱水源が必要。そういう熱源を探すことは容易ではありません。実際に掘削してみたら予想より温度が低く、発電向けには使えない、という可能性も考えられ、事業にはリスクも伴います。
私が次に訪れたのは、フルージルという南部の地にあるより小さい発電施設。いわゆるゴールデン・サークルの近辺。ちなみに近くには、「シークレット・ラグーン」と名付けられた施設もあり、ここはちょっとした観光施設にもなっています。(温泉横に作られた古いスイミング・プールをきれいに改装しただけに過ぎないのですが。ちょっと面白いところではありますが、どこが「秘密」なのかはいまだ謎です。)
地域の発電事業者によりこの施設が建設されたのは2018年のこと。新しい施設ですが、発電能力はわずかに600kWに過ぎません。しかし、ここには、「バイナリー」方式といわれる最新の発電方式の施設が設置されています。利用されているのは、117度の比較的低温の温水で、8機のクライムオン社(スウェーデン)のジェネレーターにつながり、低温で揮発する触媒を通じてタービンを回し、地域に必要な電力を生み出します。
この発電施設の運営者は、今では、スウェーデン資本のベースロード・キャピタル社の子会社となっています。ベースロード・キャピタル社の子会社は、実は日本や台湾にもあり、小規模ながら、低温熱源を地熱発電に活用する試みがなされています。こうした低温熱源の利活用は、電力料金の低いアイスランドよりも、むしろ、日本のようなところに向いているのかもしれません。