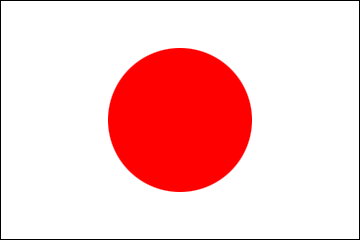大使室より(地熱の直接利用 大使館から見える風景)
令和5年7月3日

写真にあるのは、我々の働く日本大使館のすぐ近くにある構造物です。
上部に煙突のようなパイプが突き出ており、時間帯によっては、湯煙がもうもうと吹き出しています。
同様の構造物は大使館の周辺にはいくつもあります。
実は、このちょっと変わった形の構造物の下には、実は地下2千メートルに及ぶ深さの熱水井が掘られているのです。そこから吹き出る温水は、レイキャビク市内の各所に供給されています。
地熱の利用というと、電力不足の日本では地熱発電に注目が集まりがちですが、アイスランドでの地熱活用の主要な部分を占めるのは、こうした暖房用の温水供給です。そもそもアイスランドで地熱開発が始められたのは、第一次大戦中、石炭の価格が高騰したことに由来するとのこと。家庭用、病院等の建物の暖房費を押さえることが主眼だった、とか。
もちろん、これらの小さな井戸から持続的に利用可能な湯量には限りがあり、現在では、ヘトリスヘイジの地熱発電所からパイプラインで大量に運ばれる温水が、増大するレイキャビク市の温水需要の大半をまかなっていますが、市内にこのような取水井が多数あれば、パイプラインを通じて遠くから湯を運ぶ必要はなく、効率的です。
東京近辺でも、地下深く井戸を掘れば暖かい湯水が出る、と聞いたことがありますが、だとすれば、それをうまく活用できないものでしょうか。都市での地熱発電はちょっと無理にしても、大きな建物の冷房、暖房には大いに活用できそうな気がします。
上部に煙突のようなパイプが突き出ており、時間帯によっては、湯煙がもうもうと吹き出しています。
同様の構造物は大使館の周辺にはいくつもあります。
実は、このちょっと変わった形の構造物の下には、実は地下2千メートルに及ぶ深さの熱水井が掘られているのです。そこから吹き出る温水は、レイキャビク市内の各所に供給されています。
地熱の利用というと、電力不足の日本では地熱発電に注目が集まりがちですが、アイスランドでの地熱活用の主要な部分を占めるのは、こうした暖房用の温水供給です。そもそもアイスランドで地熱開発が始められたのは、第一次大戦中、石炭の価格が高騰したことに由来するとのこと。家庭用、病院等の建物の暖房費を押さえることが主眼だった、とか。
もちろん、これらの小さな井戸から持続的に利用可能な湯量には限りがあり、現在では、ヘトリスヘイジの地熱発電所からパイプラインで大量に運ばれる温水が、増大するレイキャビク市の温水需要の大半をまかなっていますが、市内にこのような取水井が多数あれば、パイプラインを通じて遠くから湯を運ぶ必要はなく、効率的です。
東京近辺でも、地下深く井戸を掘れば暖かい湯水が出る、と聞いたことがありますが、だとすれば、それをうまく活用できないものでしょうか。都市での地熱発電はちょっと無理にしても、大きな建物の冷房、暖房には大いに活用できそうな気がします。