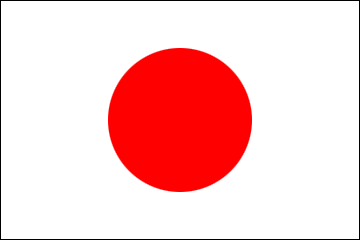大使室より(「ストックセイリの話」)
令和6年10月8日
 Photo courtesy: stokkseyri.is
Photo courtesy: stokkseyri.is
アイスランド南部、セルフォスに近い海岸沿いにストックセイリという村があります。
「村」といっても、人家も少なく、いかにももの寂れた印象のところで、高い防波堤に阻まれて道沿いからは海岸すら見えず、主要幹線からも外れているので、一般の観光客が訪れることはめったにありません。もっとも、手長エビの料理を出す結構有名なレストランが1軒だけあるので、もしかしたらそれを目的に立ち寄られた方もおられるかもしれません。(実は私もその一人ですが...。)この近辺のエイラルバッキというところにはアイスランドには数少ない刑務所もあります。
ちゃんとした港があるわけでもないこの海岸沿いの寂れたところに、何故、こうした集落があるのか、と前々から不思議に思っていたのですが、『アイスランド 海の女の人類学』(マーガレット・ウィルソン著、向井和美訳(2022)青土社)を読んで、ようやく少し事情がのみ込めました。
1800年代まで、当地で漁船といえば木造の手漕ぎの船でした。その後、帆船も登場しますが、ディーゼルエンジンのモーター船が導入されたのは20世紀に入ってからのこと。これは、アイスランドでは「産業革命」に匹敵する大事件でした。ストックセイリには、入り江と砂利の海岸があり、小さな手漕ぎ船を引き上げるのには便利だったので、古くから利用されてきたのですが、新しく登場したモーターのある大型の船を停泊させるのには不向きでした。
20世紀に入ると、そうした船が停泊可能な港が作られ、その周辺に漁業を主産業とする新しい町が形成され始めます。アイスランドで街らしい街ができるのは、実はこの時代以降のことなのです。
ストックセイリ自体は古くからの歴史あるところですが、アイスランドの産業革命の歴史の流れに取り残されてしまったようなのです。
なお、ここでは、かつてスリーズル・エイナルスドッティルという女性船長が活躍したという記録が残っています。ご関心の方は、上記の本をご参照ください。
「村」といっても、人家も少なく、いかにももの寂れた印象のところで、高い防波堤に阻まれて道沿いからは海岸すら見えず、主要幹線からも外れているので、一般の観光客が訪れることはめったにありません。もっとも、手長エビの料理を出す結構有名なレストランが1軒だけあるので、もしかしたらそれを目的に立ち寄られた方もおられるかもしれません。(実は私もその一人ですが...。)この近辺のエイラルバッキというところにはアイスランドには数少ない刑務所もあります。
ちゃんとした港があるわけでもないこの海岸沿いの寂れたところに、何故、こうした集落があるのか、と前々から不思議に思っていたのですが、『アイスランド 海の女の人類学』(マーガレット・ウィルソン著、向井和美訳(2022)青土社)を読んで、ようやく少し事情がのみ込めました。
1800年代まで、当地で漁船といえば木造の手漕ぎの船でした。その後、帆船も登場しますが、ディーゼルエンジンのモーター船が導入されたのは20世紀に入ってからのこと。これは、アイスランドでは「産業革命」に匹敵する大事件でした。ストックセイリには、入り江と砂利の海岸があり、小さな手漕ぎ船を引き上げるのには便利だったので、古くから利用されてきたのですが、新しく登場したモーターのある大型の船を停泊させるのには不向きでした。
20世紀に入ると、そうした船が停泊可能な港が作られ、その周辺に漁業を主産業とする新しい町が形成され始めます。アイスランドで街らしい街ができるのは、実はこの時代以降のことなのです。
ストックセイリ自体は古くからの歴史あるところですが、アイスランドの産業革命の歴史の流れに取り残されてしまったようなのです。
なお、ここでは、かつてスリーズル・エイナルスドッティルという女性船長が活躍したという記録が残っています。ご関心の方は、上記の本をご参照ください。